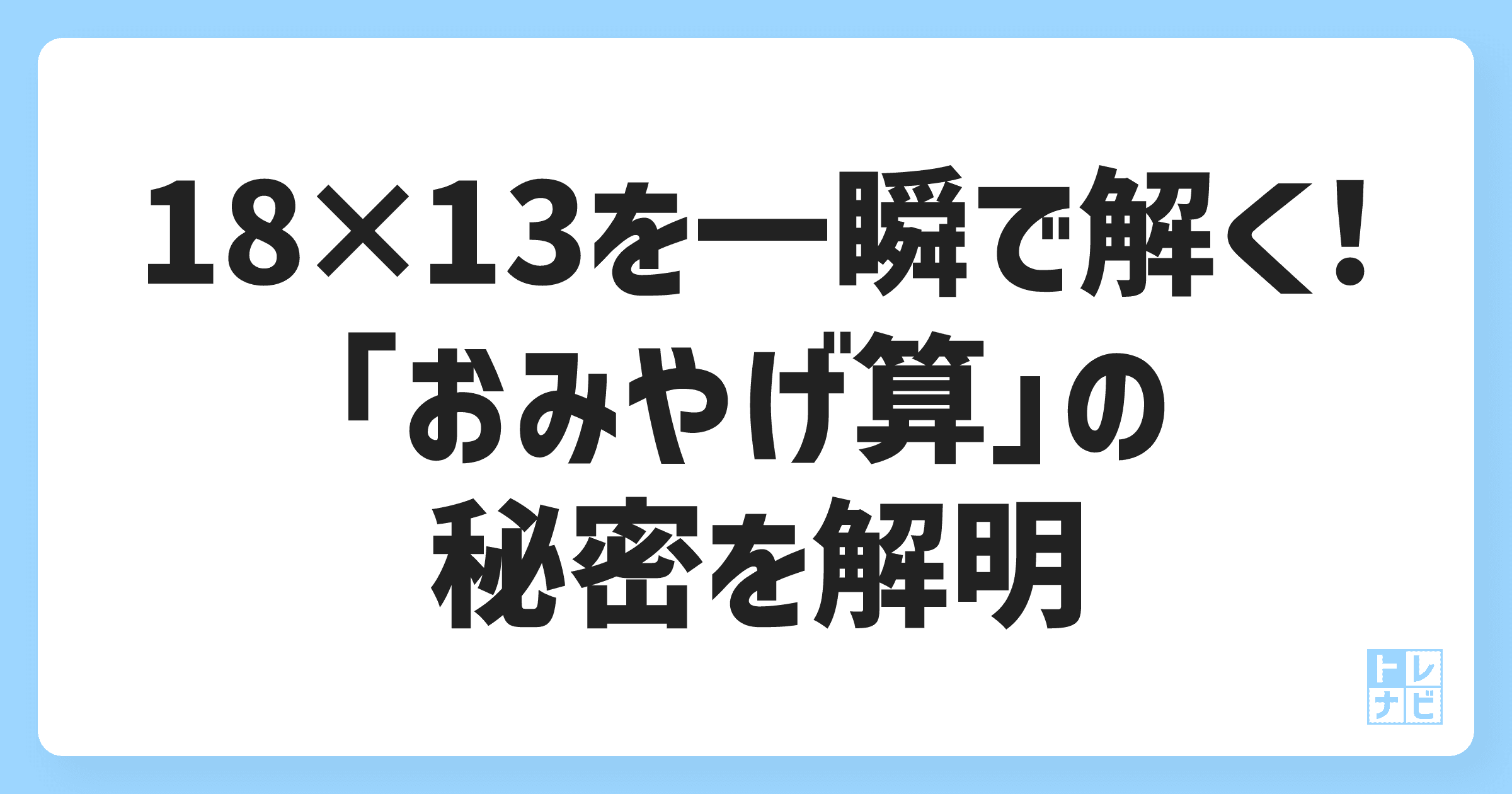
【驚愕】18×13を一瞬で解く!「おみやげ算」の秘密を解明
おみやげ算とは何か? おみやげ算とは、主に「十の位が1の2ケタの数どうしのかけ算」を瞬時に暗算するための方法です。この方法を使うと、11×11~19×19といった範囲のかけ算が簡単に計算できるようになります。例えば、「 […]

2023年は記録的な猛暑に見舞われ、その影響で米の品質が大きく低下しました。新潟県産コシヒカリでは1等米の比率が過去最低を更新し、同様の現象が他県でも観測されました。特にフェーン現象による高温は、米粒に高温障害を引き起こし、品質が著しく低下しました。これにより、米の価格が上昇し、消費者への負担も増加しています。
農家は猛暑に適応するためにさまざまな対策を講じていますが、依然として多くの課題が残っています。宮城県では暑さに強い栽培法の推進が進められていますが、これが全国的に浸透するには時間がかかります。また、高温に強い品種の開発も進められていますが、実用化にはまだ時間がかかるとされています。これらの対策は長期的な効果を期待される一方で、短期的な解決策としては不十分です。
今後の気候変動予測によると、2024年も引き続き高温の可能性が指摘されています。さらに地球温暖化の影響で、今世紀末にはコシヒカリの米粒の約7割が高温障害に影響を受ける可能性があるとされています。これにより、今後も米の品質低下と価格上昇が続くことが懸念されています。したがって、農家や政府は長期的な視点での対策を急務としています。
日本では、米の供給不足が大きな問題となっています。これには、農林水産省の政策が深く関与しています。以下では、その具体例と影響について詳しく説明します。
農林水産省の政策ミスの一例として、2023年の生産調整がうまくいかなかったことが挙げられます。この年、猛暑の影響もあり、生産量が大幅に減少しました。それにもかかわらず、インバウンド需要の増加や国際的な米の需要増加に対して適切な対応が行われなかったのです。この結果、供給量が不足し、コメの価格が著しく上昇しました。また、宮城県や新潟県など、品質低下が顕著な地域も出てきました。
農林水産省は2024年に入り、供給不足を補うための政策変更を行いました。この政策変更により、国産米の在庫を1年間提供することを保証し、国民に安心して食べるよう呼びかけています。しかし、この措置も一時的なものであり、長期的には根本的な解決策にはなりません。フェーン現象や地球温暖化の影響で、今後も米の品質や生産量に影響が出る可能性が高いです。
日本と他国の米政策を比較すると、日本の米政策にはいくつかの改善点が見えてきます。例えば、アメリカやオーストラリアでは、より計画的な生産調整が行われており、インバウンド需要や国内需要の変動にも柔軟に対応しています。また、品質管理の面でも、最新の農業技術を取り入れ、高温障害に強い品種の栽培を推進しています。これに対して、日本ではまだ伝統的な方法に依存している部分が多く、気候変動に対する対応が遅れているのが現状です。
インバウンド需要の増加は、日本の米不足に大きく影響しています。2024年7月13日付の日本経済新聞によると、令和の米騒動の一因として、このインバウンド需要の増大が挙げられています。訪日外国人観光客の増加により、特に和食文化の体験を求める観光客が増え、日本国内での米消費量が急増しました。これにより、米の価格が大幅に上昇し、大手コメ流通の幹部も「30年を振り返り、記憶にないほどの価格上昇だ」と発言しています。
外食産業の影響も無視できません。特に、和食レストランや寿司店、ラーメン店などの需要が高まり、米の消費量が急増しています。また、新型コロナウイルスの影響で一時的に停滞していた飲食店の需要が回復し、再び高まったことも影響しています。これにより、供給が追いつかなくなり、米不足が深刻化しているのです。
一方で、食生活の変化も米需要に影響を与えています。日本の人口は減少傾向にあり、それに伴い食生活も多様化しています。要するに、日本人一人あたりの米消費量は減少しているものの、インバウンド需要や外食産業の影響がこれを上回る形で総米消費量は増加しています。また、農水省の政策も長期的な視点での米供給の安定を図るために対応が求められています。2024年7月15日のライブドアニュースにおける農林水産省の冷静な対応の呼びかけは、この問題に対する一例と言えます。